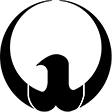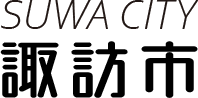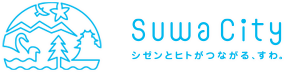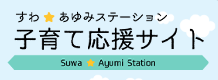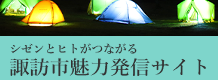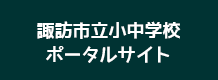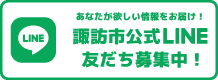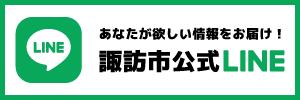本文
令和7年度 第1回 諏訪市議会議員研修会を開催しました!
令和7年度 第1回 諏訪市議会議員研修会を開催しました!
諏訪市議会では、「議員の資質向上と市民のための議会改革の実現」を目指し、岩崎弘宜(イワサキヒロマサ)(※正式には「立」さきとなります)議会改革アドバイザーをお招きし、令和7年9月27日(土)・28日(日)と2日間にわたり議員研修会を開催しました。当日の研修の内容や様子を、以下にお伝えします。
【岩崎氏略歴】
長野市出身。茨城県取手市役所総務部情報管理課長の現職。議会事務局職員歴通算27年。公務員アワード2021において、公務員アワード等受賞。また、議会改革度ランキング2020,2021において、2年連続、取手市議会、総合全国第1位獲得等、幾多の賞を受賞。公務の傍ら、市町村アカデミー、NOMA、JIAM研修講師や市町村議会議員研修会講師として日夜奮闘。長野県千曲市・埼玉県宮代町の議会改革アドバイザーとしても活躍中。


≪ 1日目 9月27日(土)午後1時30分から午後4時30分 (於)諏訪市役所大会議室 ≫
本日のテーマ「諏訪市議会における質問力の向上!」について
冒頭、牛山正議長より「議員の代表・一般質問は何を質問しても自由だと思うが、単なる現状確認だけでなく、市民の視点に立って、困りごとや、疑問を代弁する内容か、建設的な議論を促す質問か、将来の方針や改善策、政策的な提言がされているのか等、どのようにしたら良い質問となるかを教えて欲しい。そして前期より、議会改革推進特別委員会が取り組んでいる、小中学生への主権者教育について等助言いただきたい。」とあいさつがありました。
それを踏まえて初日は、「諏訪市議会における質問力の向上!」と題して研修をいただきました。また、二日目には、「先進事例に学ぶ~主権者教育(子ども会議)の進め方~」と題して研修いただくこととなりました。


【ポイント1】
諏訪市議会の会議録や代表・一般質問のYoutube配信映像を事前に確認いただいた上で、岩崎アドバイザーから、「改善が必要な一般質問」として、以下の提案をいただきました。
1.質問の焦点不足
一つの質問内でテーマが広がりすぎているとして、論点が分散し答弁が表面的になりやすくなっている、必ず自分の質問した内容を会議録やYoutube配信映像により振り返ることが望ましい。
諏訪市議会定例会のYoutube配信については、市ホームページよりアクセスすることが出来ますので、ぜひご視聴ください。
2.根拠データの不足
主張が感覚的・印象的、偏在的な表現に留まっており、反対側からの視点が不足していることから、客観的データや比較事例を添えることで説得力が増すので、事前調査を深めるべき。また、市民一人の声も大事だが、それ以外の市民にも思いをはせる必要がある。
3.政策提案の具体性不足
問題提起はあるが解決策が示されていない、または、執行部任せや方向性が曖昧な部分がある、どう改善すべきか示すことで執行部の検討が進みやすくなるのではないか。疑問を投げかけ、非難するだけでは質問では無いため、自ら改善案を検討し示すことが必要。
4.時間配分の偏り
前置きや説明が長く、質問の核心に割く時間が短いとして、限られた質問時間を有効活用するために、説明と質問のバランスを意識することが必要である。質問は言いたいことを言う時間ではなく、質(ただ)し問う時間にする必要がある。前置きや説明は資料として事前配付し、端的に話した方が良い。
5.答弁引き出し不足
イエス・ノー型の質問が多く、執行部の説明を深められていない、オープンな質問を増やすことでより詳細な答弁を引き出せるので、問答を繰り広げて展開していく形の想定問答を準備することが望ましい。ただし、イエス・ノー型の質問は不祥事の際は有効である。
【ポイント2】
6月定例会の会議録から具体的に、「一般質問として好ましくないと考えられる発言」部分等の指摘をいただいた上で、良い質問の仕方を実際にご教示いただきました。
1.論点の明確化
「どうなっているのか。」「大丈夫か。」など、背景や目的が示されず単発で投げかける質問は、執行部が具体的に答えにくく、答弁が一般論や現状説明に終始しがちなため、好ましくない。
質問冒頭で課題や背景を簡潔に提示したり、課題等をわかりやすい資料にまとめ配付することで、議員や執行部、傍聴者が論点を把握しやすく、議事録としてもわかりやすくなり後から参照しやすくなる。
また、議会質問は政策提案や改善促進が目的であり、「件数は何件か。」「予算はいくらか。」など、単なる情報取得や統計確認に留まる質問は、自ら事前に調査し、配布資料とすべきで、好ましくないと考えられる。どうしても質問する時は、その資料や認識で誤りが無いか自ら発言する必要がある。
2.地域課題との接続
質問が市民生活や地域特性に直結することで、議会質問の本旨である「市政に関する」「市民の声の代弁」として機能する。
3.具体的事例の提示
「市民はみんな困っている。」「他に比べて非常に遅れていると思う。」など、根拠となるデータや事例がない主張は、客観性に欠け、政策検証の材料として弱いため、好ましくないと考えられる。
抽象論ではなく、現場の事例や数字を交えて質問することや、事前調査をしっかりと行うことで、執行部の答弁が具体化しやすく、政策改善の方向性を引き出せる。
4.複数視点からの質問
一方向からの見方や一部に偏らず、法的枠組みや財政面、運用面など多角的な視点の論点があることで、単なる要望ではなく市政全体からの発言となり、政策検証としての質を高める。
5.再質問の活用
答弁を受けて掘り下げをせずに次の質問に移ってしまっており、政策の具体化や実施時期の明確化の機会を逃してしまっている。答弁を受けて論点を深堀りする再質問を行うことで、執行部の市政や具体策をより明確にし、課題解決につながる。ただし、議長の裁量で、通告の範囲を超えていると判断したら執行部は答えないでいいよう議事整理をする。
また、「やるのか、やらないのか。」だけで終わる質問は、執行部の説明や改善策を引き出せず、議論が深まらないため、好ましくない、また、自らのマニフェストの重点課題に関しては、長年改善が見られないときに「やるのか、やらないのか。」問いただすことは有効ではあるが、ハラスメントと受け取られないように配慮をする必要がある。
【ポイント3】
実際にやってみよう、ということで「災害時の避難所運営体制の強化を」を題材に模擬一般質問の作成を行いました。
「論点の絞り込みやデータの裏付け、政策提案の具体化を強化すれば、議会として政策形成機能をさらに高められる。特に、問題提起、根拠提示、改善案提示、再質問という流れを意識すると、一議員の発言が議会基本条例に定める政策提言としての効果や議会による行政の監視機能として有効な行動に繋がり、その価値が高まるのではないか。」との言葉で、1日目の「諏訪市議会における質問力向上!」の研修を終えました。




≪ 2日目 9月28日(日)午前9時30分から午後0時07分 (於)諏訪市役所大会議室 ≫
まずは、昨年度に引き続き「皆さんからいただいた課題解決に向けて」をテーマとして、
- 他自治体の状況を調査するなど、まだまだ議会に出席するまでにやれること、やらなければいけないこと、やった方がいいことをやり切っていない。
- これまでの背景や流れを事前調査し、議長の許可を得て資料として議場配付をしましょう。そして、自分で調査したことは自分の言葉で述べ、誤認識していないか質(ただ)す。その上で、市政に関する提言、市政の誤りの改善指摘を展開。
- 事実をありのままに、様々な手段を用い、タイムリーに発信する。
- 住民の元へ出向く。
- 政策提言の提出の際に、執行機関から回答を要するものがあれば、「期日までに本職へ処理状況を報告願います。」と鑑に一文入れておく。必要なら、対面で回答文書の受け取りをし、そこへ書かれていない(書きにくい)状況や経過を意見交換する。
- どこかのタイミングで質問より討議を優先し、真に市民に役立つ議論の存在に変わる第一歩を踏み出しては。 等
以上、多くの提案・提言等をいただきました。
続いて、「先進事例に学ぶ~主権者教育(子ども会議)の進め方~」と題して研修いただくこととなりました。
【おさらい】
はじめに、昨年度の研修でもご紹介いただいた、茨城県取手市議会における中学生議会の進め方を改めてご紹介いただきました。
【ポイント】
学生との事業を成功させるために、学校側の負担をかけず議会側で出来ることはすべて行うこと、生徒の自主性に重きを置きなるべくリアルを追求しシナリオは最小限とすること、議員と生徒が一緒に考え、体験し、成果を共有する仕組みを作ることをご助言いただきました。
成功のための基本方針
- 模擬議会、政策提言ワークショップなど参加型の形式が効果的。
- 学校生活や防災など学生にとって身近な課題を題材にする。
- 議員が一方的に話すのではなく、生徒の意見を引き出し、議員が答える構造にする。 等
実践アイディア
- 模擬議会、模擬選挙
- ワークショップ
- 成果発表展示 等
実務的な工夫
- 事前学習
- 振り返りシートや事前事後アンケート 等
「学生との事業を成功させるための秘訣は、とにかく学校に負担をかけないこと。議会でしっかりと役割分担をし、全員が汗を流す必要がある。実際の授業では、議員と生徒が一緒に考える時間をなるべく多くとり、議員が道筋は作ってあげたとしても、あくまでも最後に決めるのは学生とすることが大事ではないか。」との言葉で、二日間の研修を終えました。
最後に
今回の研修では、議会改革アドバイザーの岩崎弘宜氏を講師に、代表質問・一般質問や議会運営の課題について多角的な視点から学ぶことができました。
議会での発言は、市の未来を形づくる貴重な機会であります、市民の希望を力強く届ける議員になるようこれからも、さらに研鑽を積んでまいります。
諏訪市議会議長 牛山 正