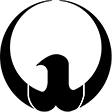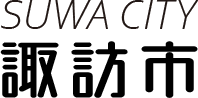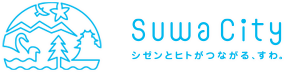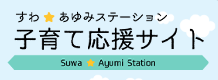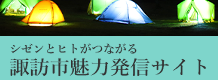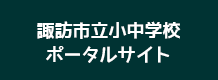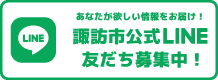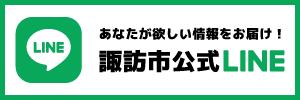本文
福祉医療費の申請手続き
福祉医療費の申請手続き
必要な手続き
1.受給者証交付申請
資格区分に応じ、福祉医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/122KB]と資格区分に応じた必要書類をお持ちいただき、市役所市民課国保医療係窓口へ申請してください。
(※交付申請書記載例:子ども [PDFファイル/338KB]・障がい [PDFファイル/338KB])
申請をすると、「福祉医療費受給者証」 が交付されます。
| 資格区分 | 必要書類(申請書以外) | 全資格共通 |
|---|---|---|
| 子ども | なし |
|
| 重度心身障害者・児 | 障害の程度がわかる書類(手帳等) | |
| ひとり親家庭等 |
・18歳以上20歳未満で高校等に在学中の子どもがいる時は、在学証明書 |
受給者証の有効期間は通常7月31日までとなっており、年1回新しい証が交付されます。
※「子ども」の資格に該当する方は、有効期間が異なります。
※資格により短い有効期間の方もいます。
2.支給申請手続き
支給申請手続きが不要な場合
- 長野県内の病院・歯科医院・薬局の場合(受給者証を提示すれば、医療機関で手続きをしてもらえます。必ず窓口で受給者証を提示してください。)
支給申請手続きが必要な場合
- 長野県外の医療機関を受診した場合
- 受給者証の提示をしなかった場合
- 医療機関で現物給付方式に対応できない場合(18歳到達後の最初の3月31日までの方のみ)
- 治療用装具を作製した場合(弱視用メガネ、補装具等) ※下記「療養費の場合」をご参照ください。
【支給申請に必要なもの】
- 福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/67KB]・福祉医療費支給申請書[Wordファイル/54KB]
- 医療機関の領収書(原本)
- 福祉医療費受給者証
- 被保険者であることを示す書類(資格確認書等)
- 申請にお越しになる方の本人確認書類
※注意点1(療養費の場合)
- 小児弱視による眼鏡作成や補装具等で全額自己負担した場合は受給者証は使えません。その場合、加入している医療保険へ療養費の申請をすると、自己負担分を除いた額(未就学児は8割、70歳未満の人は7割、70歳以上の人は7割または8割もしくは9割)が後日払い戻されます。
- 療養費の申請時に医師の証明書、領収書の原本を提出しますので、福祉医療費申請のためにコピーをとっておいてください。払い戻しがありましたら、医師の証明書・領収書のコピー、加入医療保険からの療養費の振込通知のコピーを「福祉医療費支給申請書」に添付して、市役所へ支給申請をしてください。
※注意点2(申請)
- 領収書は診療を受けた方がわかるものをご提出ください。レシートの場合には氏名を記入してもらい、医療機関の認印をもらってください。
- 申請書は月別・病院別に、また入院・外来別(薬局も別)に1枚ずつ作成してください。
- 医療を受けた月から1年以内に申請してください。
※記入方法等ご不明な点はお問い合わせ下さい。