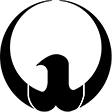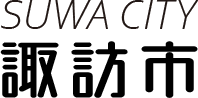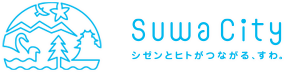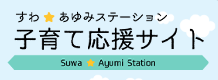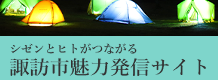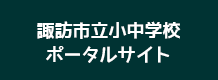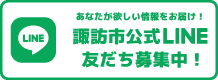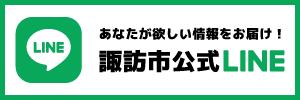本文
国民健康保険税の軽減・減免制度
国民健康保険税の「軽減」
低所得者の軽減制度(※申請不要)
所得の少ない方の税負担を軽くするため、総所得金額が一定以下の世帯について、均等割額・平等割額を軽減する制度です。
- 7割軽減世帯…前年の総所得金額等が43万円※1+{(世帯内の給与所得者等※2の数-1)×10万円}以下の世帯
- 5割軽減世帯…前年の総所得金額等が43万円※1+{(世帯内の給与所得者等※2の数-1)×10万円}+(30.5万円×被保険者数等)以下の世帯
- 2割軽減世帯…前年の総所得金額等が43万円※1+{(世帯内の給与所得者等※2の数-1)×10万円}+(56万円×被保険者数等)以下の世帯
※1 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
※2 給与所得者等とは、次のいずれかに該当する世帯主(国保への加入の有無を問わない)及び世帯内の被保険者等を指します。(1)前年の給与収入額が55万円を超える人、(2)65歳未満で公的年金収入額が60万円を超える人、(3)65歳以上で公的年金収入額が125万円を超える人
※3 国保加入者が軽減に該当する場合でも、国保に加入していない世帯主に基準を上回る所得がある場合は、その世帯の低所得者軽減は適用されません。
※4 所得がない人でも、その旨を住民税申告しないと軽減適用を受けることはできません。
非自発的失業者に対する軽減制度
倒産や解雇、病気等により失業(離職)され国保へ加入した場合、国保税の所得割額を減額する制度で、失業した方の前年の給与所得金額を100分の30とみなして国保税額の算定を行います。(給与所得以外の所得は軽減されません。)
対象者
以下条件を両方とも満たす必要があります
- 失業(離職)時点で65歳未満の方
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが下記の方
- 「特定受給資格者」(倒産、解雇、雇い止めなどによる離職)…11・12・21・22・31・32
- 「特定理由離職者」(雇用期間満了や正当な理由のある自己都合による離職等)…23・33・34
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで
申請方法
必要書類がそろっていれば電子申請が便利です
【方法1:電子申請(スマホやパソコンで申請)】
- 電子申請リンク<外部リンク>
- 必要書類は記載内容が確認できるようにスマホ等で撮影した画像を添付して下さい
- 申請にはメールアドレスが必要です
【方法2:来庁】
- 必要書類を持参し来庁してください
【郵送3:郵送】
- 手続きに必要なもの(必要書類はコピー)をそろえて諏訪市役所市民課国保医療係へ郵送してください
- 郵送先:〒392-8511 諏訪市役所市民課国保医療係
手続きに必要なもの
- 非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申請書(申請書[PDFファイル/58KB]、申請書[Wordファイル/23KB])
- 電子申請の場合は不要です
- 来庁手続きの場合は窓口でお渡しします
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等・顔写真付きのもの)
未就学児に対する軽減制度(※申請不要)
国民健康保険加入者のうち未就学児の均等割額(1.低所得者の軽減制度に該当する場合は、減額後の金額)を、5割減額する制度です。
出産予定の被保険者に対する軽減制度
出産予定の国民健康保険加入者に対し、所得割・均等割を軽減する制度です。
- 軽減内容…出産予定(または出産した)の方の所得割及び均等割を免除
- 軽減期間…出産予定月(または出産月)の前月から4か月間(双子以上は3か月前から6か月間)
- その他…出生届提出時に申請のご案内をします。事前申請も可能です。その場合には、出産予定日の分かるもの(母子手帳など)をお持ちください。
後期高齢者医療制度移行に伴う国保税の軽減制度
後期高齢者医療制度に加入している人がいる世帯の軽減制度です。
- ご家族の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の国保加入者が1名となった世帯について、平等割が最大8年間軽減されます。(5年間2分の1、その後3年間4分の1) (※申請不要)
- 後期高齢者医療制度に移行した方が被用者保険(社会保険)の本人で、その方の被扶養者だった65~74歳のご家族が国保に加入した場合、国保税の軽減措置があります。 (※要申請)
国民健康保険税の「減免」
※減免制度について、詳細はお問い合わせください。
国民健康保険税の減免制度
下記のような特別な理由があり、生活が困難であると認められるなど、一定の要件を満たす場合、国民健康保険税の一部または全額が減免されます。減免には申請が必要です。
- 死亡や障害者となったことによる生活困窮
- 失業や廃業による生活困窮
- 疾病や負傷による生活困窮
- 災害による資産への重大な被災
- 国民健康保険法第59条各号への該当
【参考:生活困窮状態判断基準の一部】
- 現金、預貯金及び有価証券の保有総額については、生活保護の要否決定に準じて算出した生活認定基準額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準生活費」という。)の6月分を超えないこと。
- 上記を除く資産については、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の要否判定基準を超えないこと。
- 申請日の属する月の前1月における収入額と基準生活費との比較により算出した率が100分の120未満であること。
一部負担金の減免制度
災害や貧困などの特別な理由があり、一定の要件を満たす場合、保険医療機関等窓口で支払う一部負担金が免除となる制度があります。
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯の生計主体者が死亡したり、障害者となったり、資産に重大な損害を受けた時など、生活が著しく困難となった場合において、最大6ヶ月間(割合はそれぞれ異なります)減免を受けることができます。減免には申請が必要です。